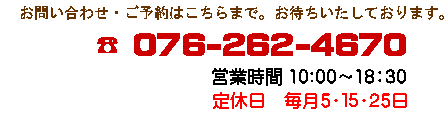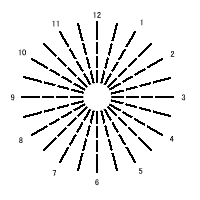お問い合わせをお待ちしております
TEL. 076-262-4670
営業時間 AM10:00 ~ PM18:30
乱視検査
乱視について
乱視は、「乱れる」という文字が入っていますので、「何か悪いもの」というイメージを抱く方が多いですが、実はさほど深刻なものではないことがほとんどです。
眼の方向により屈折力に違いがある状態を乱視といい、レンズとしての眼が完全な球面でないことを意味します。
完全な球面を実現するというのはなかなか難しいことですから、乱視があるのは決して異常なことではなく、むしろ当然とも言えます。
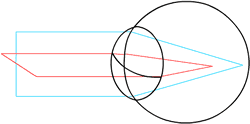 |
無限遠から来た平行光線が、点として結像しない屈折状態と説明されます。具体的には点光源が、円・楕円・焦線となり、点として結像しないため明視できません。 最も屈折の強い方向を強主経線、弱い方向を弱主経線といいますが、 主経線(互いに直交している)の方向によって倒乱視、直乱視、斜乱視とも呼ばれますが、詳しい説明は省きます。
|
|
上図では水平方向の光線(赤)と |
人によっては、乱視が眼精疲労の原因になることもあります。
乱視による眼精疲労は、乱視を適正に矯正することで解消されます。
乱視の検査
■ 乱視の自覚的屈折検査
乱視の自覚的屈折検査(お客様にお答えを委ねる測定)は、以下の二つあります。
|
●クロスシリンダー法 |
クロスシリンダーという道具を使って測定します。 左:反転クロスシリンダー
|
|
●放射線乱視表測定 |
主に雲霧法と呼ばれる屈折検査法で使われる乱視測定用の視標です。 |
|
一般的には、クロスシリンダー法が「精密乱視測定法」などと呼ばれることが多く、 |
|
●当店では、より正確を期するために、 主にクロスシリンダーを用い、
「両眼開放屈折検査」と組み合わせて乱視の測定をしています。
■ 乱視矯正による空間の違和感
乱視眼は眼球の方向により屈折が異なる眼です。
これを、 方向によりレンズの度数が異なるレンズで打ち消して矯正するのが乱視レンズです。
そのため、網膜像の拡大率が方向により違ってくるために、像が縦長に見えたり、横長に見えたり、傾いて見えたりすることがあります。
しかし、人間の脳は良くしたもので、このような違和感を取り除く処理能力ももっています。
その処理能力は個人差があり、直ぐ処理できるかたもいますし、なかかな処理できないかたもいます。
乱視度数が弱ければ簡単に処理できるというものでもありませんし、
大丈夫かなと思うような強い乱視でも直ぐに馴染んでしまうかたもおられます。
馴染み具合は、屈折度数、過去の矯正歴、レンズと角膜の頂点間距離、または性格など、多種多様な要因にわたります。
■ 快適な乱視矯正メガネ作り
当たり前のことですが、乱視による視力の低下や眼精疲労は、乱視を適正に矯正することで解消されます。
しかし、乱視矯正による違和感が強いと、それもままならなくなります。
特に乱視の軸方向が180°や90°ではない「斜乱視」という状態では違和感が起こりやすくなります。
メガネは、より良く見るために使う道具ですから、視力が低すぎるメガネでは快適とはいえません。
当然、良く見えて、違和感が少ないほうがいいにきまっているのですが、往々にして
・良く見えるけれども、違和感が強い。
・違和感は少ないけれども、あまり良く見えない。
ということが起こりがちです。
こんな時は、「違和感の少なさ」と「より良い視力」という矛盾を、
高い次元で調和していく繊細な乱視合わせのテクニックが必要になります。
さて、ご自分の眼鏡の正確な度数はご存知ですか?
例えば、眼科で発行される処方箋や、
一部のレンズメーカーより発行される度数等が印刷されたデータカードなどに書かれたこんな数字です。
SPH -3.00D CYL -1.50D AX 180°
SPHは球面レンズの度数、
CYLは円柱レンズの度数、
AXは円柱レンズの軸方向となります。(円柱レンズは乱視レンズと読み替えていただいて結構です。)
さて、人間の眼は、精密なマシンで研磨されたレンズではありません。
乱視軸が正確に90度、180度といったキリの良い角度で存在することは意外に少ないものです。
乱視軸が180度と処方されていても、正確に測れば、5度であったり、172度であったりすることも多々有ります。
乱視を正確に測るには、時間と技術が必要です。それが無い場合、往々にしてキリの良い方向に入れてしまいがちになります。
あるいは、空間の違和感の軽減のために、あえて角度を水平・垂直にズラすという考え方もあるでしょうが、
それでは乱視矯正の効果がガクンと落ちてしまいます。
目の乱視軸とメガネの乱視軸がずれると、新たな乱視が合成され、残余乱視となり現れます。
|
例1: |
残余乱視の量から換算すると、乱視軸が
5°ずれると 18%
10°ずれると 34%
15°ずれると 53%
20°ずれると 68%
25°ずれると 84%
30°ずれると 100%
も乱視矯正効果が落ちてしまうのです。
当店では、乱視の角度は可能な限り細かく測定し、1度単位で記録しています。
そして、違和感と見え方を高い次元で調和できるように、度数の入れ方を工夫し、お客様と相談しながら度数を決めていきます。
※ ご注意 ※
正確な乱視の検査を行うには、それなりの時間が掛かります。
「オートレフで得られた他覚的検査データをそのまま装用し、レッドグリーン視標で過矯正の確認をするだけ」
あるいは 「オートレフで得られた乱視軸はそのままに、乱視度数だけ自覚的測定する」
という安易な検査を行う眼鏡店もあるようですが、当然のことながら好適な装用度数が得られるとは限りません。
不適切な乱視の矯正は、違和感や眼精疲労につながりますのでご注意ください。
乱視メガネ研究会
のHPもご覧ください
その他、こちらもご覧ください
| 深視力検査 |
お問い合わせ
![]() 電話番号: 076-262-4670
電話番号: 076-262-4670
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
メールでのお問い合わせ
*ご質問等に対する弊社からの返信が、各プロバイダ様のサーバーエラーにより未達となる場合がございます。返信メールアドレス、メールプログラムの設定等ご確認くださいませ。
尚、個別商品の品番等の問い合わせにはお答えいたしかねますのでご了承ください。